【吉祥寺徒歩1分】武蔵野市・三鷹市・杉並区のパーキンソン病外来|神経内科専門医が診療
パーキンソン病は、動作が遅くなる、手足のふるえ、筋肉のこわばり、
バランスのとりにくさなどの運動症状を中心とした病気です。
あわせて、においの低下、便秘、レム睡眠行動障害(RBD)など、
からだの中の変化や眠りの変化がみられることもあります[1]。
診断は、診察で動きの特徴(動作の遅さ・静止時のふるえ・筋肉のこわばりなど)を確認し、
他の病気による似た症状(脳梗塞や薬の副作用など)をていねいに除外していくことで行います[1]。
世界的には人口の高齢化などの影響で患者さんが増え続けており、
「パーキンソン病パンデミック」という言葉が使われるようになってきました[17]。
一方で、適切なお薬やリハビリを組み合わせることで、長く生活の質を保てる時代にもなってきています[3][4]。
吉祥寺おおさき内科・脳神経内科(吉祥寺駅徒歩1分)では、
神経内科専門医が診断から薬物療法・リハビリ・生活指導までを行い、
必要に応じてDAT‑SPECTやMIBG心筋シンチグラフィーなどの核医学検査も近隣の医療機関と連携してご提案します[16][18]。
目次
- パーキンソン病とは(どんな病気? 年齢との関係)
- こんな症状があればご相談ください(パーキンソン病)
- パーキンソン病の症状(運動・非運動)
- パーキンソン病の原因(神経変性のしくみ)
- パーキンソン病の初期に出やすいサイン
- レム睡眠行動障害(RBD)とは
- パーキンソン病の治療(薬・進行期治療・生活)
- 当院に通院される方のイメージ(ケースストーリー)
- よくある質問(FAQ)
- 関連するページ(パーキンソン病)
- 参考文献
要点サマリー(このページで分かること)
- パーキンソン病がどんな病気か、年齢との関係や世界的に患者さんが増えている背景を大まかに把握できます。
- 初期に出やすいサイン(ふるえ・動作の遅さ・においの低下・便秘・レム睡眠行動障害など)と、受診の目安を整理できます。
- 運動症状と非運動症状の全体像や、DAT‑SPECT・MIBG心筋シンチグラフィーなどの検査がどのような場面で役立つかのイメージがつきます。
- 薬物療法・進行期治療・リハビリ・生活の工夫を、当院での実際の診療の流れとあわせて俯瞰できます。
パーキンソン病とは(どんな病気? 年齢との関係)
パーキンソン病は、脳の黒質(こくしつ)という部分で、ドパミンを出す神経細胞がゆっくり減っていく病気です。
ドパミンが少なくなると、体の動きをなめらかに調整する機能が弱くなり、動作の遅さやふるえなどが出てきます[1]。
年齢とともに増える病気です
パーキンソン病は、若い方でも起こりえますが、多くは中高年以降に発症します。
世界の研究では、60歳以上ではおよそ100人に1人(約1%)、80歳以上では2%前後の方がパーキンソン病と推定されています[1][3]。
世界全体で「パーキンソン病パンデミック」と呼ばれています
世界的には、人口の高齢化・寿命の延び・工業化や農薬使用などの環境要因の影響で、パーキンソン病の患者さんは今後も増え続けると予測されています。
国際的な研究グループは、パーキンソン病が最も速く増加している神経疾患の一つであり、今後数十年で患者数がさらに倍増する可能性があるとして、「パーキンソン病パンデミック」という言葉で警鐘を鳴らしています[17]。
もちろん、「高齢になれば必ずパーキンソン病になる」という意味ではありませんが、
高齢化が進む社会では、パーキンソン病とどう向き合うかが大きなテーマになりつつあります。
当院では、年齢や生活背景をふまえて、今の症状が本当にパーキンソン病によるものかどうかを一歩ずつ確認していきます。
年齢別有病率の棒グラフ(世界メタ解析より)
※図の値は10万人あたりです。例えば2181/10万人 ≈ 2.18%(80歳以上)。地域差・診断基準・調査手法により推定値は変動します[1][3]。
こんな症状があればご相談ください(パーキンソン病)
パーキンソン病かどうかを、ご自分だけで判断するのはとても難しいものです。
「年のせいかな?」と思っているうちに、少しずつ進行していることもあります。
代表的な症状を、チェックしやすいように表にまとめました。
| 症状の種類 | 具体的な例 | チェックの目安 |
|---|---|---|
| 手足のふるえ | 片側の手や足に、じっとしているときのふるえが続く。 | 数週間以上続く/疲れだけでは説明がつかない。 |
| 動作の遅さ・細かい動作のしにくさ | ボタンをとめる、字を書く、箸を使うなどに時間がかかるようになった。 | 以前と比べて明らかに「もたつく」と感じる。 |
| 歩き方の変化 | 歩幅が小さくなり、すり足気味になる/歩き出しが重たい。 | 家族から「歩き方が変わった」と指摘される。 |
| 表情・声の変化 | 表情が乏しい、声が小さく単調になったと言われる。 | 写真や動画を見返すと、以前より表情が固い。 |
| においの低下 | 香水や料理、シャンプーなどのにおいを感じにくい。 | 半年以上続く/風邪や鼻炎がないのに続いている。 |
| 便秘 | 3日以上出ないことが多い/下剤なしではスッキリ出ない。 | 生活を工夫しても続く頑固な便秘。 |
| 睡眠中の異常行動 | 大きな寝言、手足を振り回す、ベッドから落ちそうになるなど、夢に合わせた行動が見られる。 | 週に何度も起こる/同室の家族が心配している。 |
| 立ちくらみ・ふらつき | 立ち上がるとふらふらする/血圧が低めで倒れそうになることがある。 | 転倒につながりそうなふらつきが増えている。 |
ひとつでも気になる項目があれば、「年のせい」と決めつけずに一度ご相談いただくことをおすすめします。
パーキンソン病以外の原因のこともありますが、診断をはっきりさせるだけでも安心材料になります[1]。
パーキンソン病の症状(運動症状・非運動症状)
パーキンソン病の症状は、大きく「運動症状」と「非運動症状」に分けられます[1]。
主なものを表にまとめました。
| 分類 | 症状 | 具体的な内容・日常での気づき方 |
|---|---|---|
| 運動症状 | 動作の遅さ(寡動) | 歩き始めに時間がかかる/服の着替えや家事に以前より時間がかかる/字がだんだん小さくなる など。 |
| 静止時のふるえ | 椅子に座っているときなど、じっとしているときに片方の手や足が「ピクピク」「ブルブル」とふるえる。動かしている間は目立たないこともあります。 | |
| 筋肉のこわばり | 腕や脚を動かそうとすると固く感じる/肩こりや関節の動かしにくさとして自覚されることもあります。 | |
| 姿勢・バランスの障害 | 前かがみの姿勢になりやすい/歩いているうちに早足になって止まりにくい/ちょっとした段差でつまずきやすい など。 | |
| 非運動症状 | 嗅覚低下 | 香水・料理・ガスの臭いなどを感じにくい。風邪や鼻炎がないのに何か月も続くことがあります。 |
| 自律神経症状 | 頑固な便秘、頻尿・夜間多尿、立ちくらみ(起立性低血圧)など。 | |
| 気分・意欲の変化 | うつっぽさ、不安、何となくやる気が出ない・楽しめないなど、感情面の変化がみられることがあります。 | |
| 睡眠のトラブル | 途中で何度も目が覚める、日中の強い眠気、レム睡眠行動障害(叫ぶ・暴れる夢)など。 | |
| 認知機能の変化 | 病気が進むにつれて、もの忘れや考えるスピードの低下が目立ってくることがあります。 |
パーキンソン病の原因(神経変性のしくみ)
脳の黒質でドパミン神経が減ること、そしてαシヌクレインというタンパク質がたまりやすくなることが特徴です。
このように、αシヌクレインが脳などにたまっていくタイプの病気をまとめてαシヌクレイノパチーと呼び、
パーキンソン病などが含まれます[6]。
パーキンソン病の発症には、ひとつの原因だけでなく、加齢、環境(例:農薬・大気汚染・溶剤など)、 体質や遺伝的な要因が重なって関わると考えられています[3]。
パーキンソン病の初期に出やすいサイン
症状がはっきり出る前の「前駆期」から、いくつかの手がかりが集まると将来の発症リスクを見積もることができます。
専門的には「尤度比(ゆうどひ)」という指標を使いますが、ここでは分かりやすく強さのイメージで示します[7]。
パーキンソン病の前駆期の主な手がかり(強さ表示)
※DAT‑SPECT:Ioflupane(123I)SPECT(DaTSCAN)。保険適用・適応や読影は医師へご相談ください。
レム睡眠行動障害(RBD)とは
夢を見ている睡眠(レム睡眠)では本来、体の筋肉はゆるんでいます。
レム睡眠行動障害ではそのブレーキが外れ、夢の内容に合わせて叫ぶ・手足をふる・起き上がるなどが起こります。
本人や同室者がけがをすることがあり注意が必要です。治療は寝室の安全対策+薬物療法です[10]。
RBDに対する薬の効果
まずは、ベッド周囲の整理やマットレスの工夫など、寝室の安全対策が基本になります。
そのうえで、必要に応じて
- クロナゼパムなど
を用いることで、異常な行動を減らす効果が期待できると報告されています[10][11]。
一方で、眠気・ふらつき・転倒などの副作用が出ることもあるため、年齢や持病を考慮した慎重な調整が必要です。
パーキンソン病の治療(薬・進行期治療・生活)
治療全体の位置づけ:
- 「お薬による治療」は、初期〜中期から用いる内服の設計図。目的は主症状の緩和とオン時間の最適化、副作用の最小化です。
- 「進行期の治療」は、内服だけでは制御困難な日内変動・運動合併症に対する持続投与・デバイス補助療法の選択肢です。
- 「生活・リハビリ」は全病期の土台で、転倒予防・睡眠の安全・栄養・住環境整備によって、内服や機器治療の効果を最大化します。
1)お薬による治療(初期〜中期の中心)
お薬による治療は、主に次の3つのグループを組み合わせて行います[1][4]。
| 薬の種類 | 主な役割 | よくみられる副作用・注意点 | 使うことが多い場面の例 |
|---|---|---|---|
| レボドパ製剤 | 不足しているドパミンを補い、運動症状を最も強く改善する中心的なお薬。 | 吐き気・立ちくらみ、長期的にはウェアリングオフやジスキネジアが問題になることがあります。 | 多くのガイドラインで初期治療の第一選択とされ、高齢の方でも使いやすいとされています。 |
| ドパミン作動薬 | ドパミン受容体を直接刺激して、レボドパと似た働きを補います。 | 眠気、むくみ、幻覚、衝動性の変化(買い物・ギャンブルなど)に注意が必要です。 | 比較的若い方で、レボドパと組み合わせて使うことが多いですが、高齢の方や精神症状がある場合は慎重に検討します。 |
| MAO‑B阻害薬・COMT阻害薬など | ドパミンの分解を抑えて、薬の効き目を長持ちさせる補助的なお薬。 | 眠気・不眠・下痢など。まれに他のお薬との相互作用に注意が必要です。 | レボドパの効き目が切れてくる「ウェアリングオフ」が目立つときに、レボドパに追加して使うことが多いです。 |
これらのお薬は、「今の症状」「生活のリズム」「副作用の出方」を見ながら、少しずつ量や組み合わせを調整していきます。
2)主に進行期の治療
| 治療 | しくみ | 対象の目安 | 効果の目安/注意点 |
|---|---|---|---|
| 空腸投与用レボドパ・カルビドパ腸用液(LCIG:デュオドーパ) | 腹部の管(PEG‑J)から持続的にレボドパを送る。 | 内服で調整しにくいオフが多い方。 | オフ時間を追加で約2時間短縮した試験がありますが、機器・手技に伴う合併症に注意が必要です[12]。 |
| レボドパ持続皮下投与(ホスレボドパ/ホスカルビドパ:ヴィアレブ) | 皮下から24時間持続投与する前駆体製剤。 | 進行期で日内変動が大きい方。 | オン時間延長・オフ短縮が報告されていますが、注入部の皮下結節・発赤など局所反応に注意します[13]。 |
| 脳深部刺激療法(DBS) | 脳の特定部位(STN/GPiなど)を電気刺激して神経回路のバランスを整える治療。 | 薬で十分に調整できない運動合併症がある方。 | 運動症状・日内変動の改善が期待できますが、L‑dopa反応性が保たれていること、重度の認知機能低下や制御困難な精神症状がないことなど、適応条件があります[14]。 |
3)生活とリハビリの工夫
近年の研究では、運動や理学療法がパーキンソン病の運動症状や生活の質の改善に役立つことが示されています[5][6]。
また、転倒予防や睡眠・便秘の対策もとても重要です[15]。
| 分野 | 具体的な工夫 | 目的・エビデンス |
|---|---|---|
| 運動・リハビリ |
・速歩きやエアロバイクなどの有酸素運動 ・ストレッチ・筋力トレーニング ・バランス訓練(片脚立ち、ステップ練習など) |
運動症状(UPDRS)や歩行・バランス、生活の質の改善に役立つことが、複数の研究・メタ解析で示されています[5][6]。 |
| 転倒予防・住環境 |
・段差を減らす/スロープにする ・廊下・トイレ・浴室に手すりをつける ・夜間の足元灯・センサーライトを設置する ・カーペットやコードなど「ひっかかる物」を減らす |
パーキンソン病の方は転倒リスクが高く、環境整備が転倒予防に重要とされています[15]。 |
| 便秘・栄養 |
・水分と食物繊維を意識してとる ・適度な運動で腸の動きを促す ・必要に応じて下剤を調整し、無理に我慢しない ・やせすぎないよう、十分なカロリーとたんぱく質をとる |
便秘や栄養不足は、症状の悪化や転倒リスクの増加につながります。早めに相談し、整えていくことが大切です[1]。 |
| 睡眠 |
・寝室を暗く静かに保つ ・寝る前のスマホ・アルコール・カフェインを控える ・RBDが疑われる場合は、ベッド周囲の安全を確保する ・眠気や不眠を強める薬がないかチェックする |
睡眠障害やRBDは、日中の活動性や将来のリスクにも関わるため、環境調整と薬の見直しが重要です[1][10]。 |
当院に通院される方のイメージ(ケースストーリー)
ケース1:70代・男性「ふるえは年のせいだと思っていた」
70代前半の男性。数年前から「左手のふるえ」が気になっていましたが、
「年齢のせい」「疲れたときだけだろう」と様子を見ておられました。
最近になって、
- 字が小さくなって書きにくい
- 歩き出しが重く、つまずきやすい
といった変化にご本人とご家族が気づき、当院を受診されました。
神経内科専門医の診察と血液検査を行い、脳の他の病気を除外するために近隣の病院で頭部MRIを撮影したところ、大きな異常はありませんでした。
ふるえの原因をより詳しく評価するため、DAT‑SPECT(ドパミントランスポーターSPECT)を行ったところ、
線条体での取り込み低下がみられ、パーキンソン病に合致する所見でした[16]。
レボドパ製剤を少量から開始し、1〜2か月かけて量を調整したところ、
- ふるえがほとんど気にならなくなり
- 歩くスピードが上がって外出の回数も増えた
とのことでした。現在は、地域のリハビリと並行しながら、趣味の散歩と家庭菜園を楽しんでおられます。
ケース2:60代・女性「夜中に暴れるようになって心配に」
60代後半の女性。数年前から、
- 「夫が寝ている間に大きな声を出している」
- 「寝返りの勢いでベッドから落ちそうになった」
と家族に言われるようになりました。ご本人にも、
- 夢の中で誰かに追いかけられている
- 手を振り回した記憶がある
といった自覚があり、「レム睡眠行動障害では?」と不安になって受診されました。
当院で問診・診察を行い、パーキンソン病の初期、レム睡眠行動障害(RBD)が強く疑われました。
パーキンソン病を評価する目的で、 MIBG心筋シンチグラフィー(心臓交感神経の働きをみる核医学検査)を施行したところ、 パーキンソン病に合致する取り込み低下が確認されました[18]。
まず、
- 寝室の安全対策(ベッド周囲の片づけ、角の保護、マットレスの工夫)
を行い、そのうえで少量の薬を使っていただいたところ、
- 危険な行動はほとんど見られなくなり
- ご本人もご家族も安心して眠れるようになりました
とのことでした。
現在も神経診察を含めたフォローを続け、症状の変化や検査結果を確認しながら経過観察を行っています。
当院でできる検査・治療
「ここで何ができるのか?」が一目で分かるように、当院の役割をまとめました。
検査機器や入院が必要な精密検査については、近隣の基幹病院と連携して対応いたします。
| 検査・治療 | 内容 | 当院での対応 |
|---|---|---|
| 神経内科専門医による診察 | 問診・神経診察を行い、パーキンソン病かどうか、他の病気の可能性はないかを丁寧に評価します。 | 初診から再診まで継続してフォローし、必要に応じて検査や治療方針を見直します。 |
| 血液検査 | 甲状腺・肝腎機能・ビタミンなどを確認し、他の病気やお薬の影響がないかを調べます。 | 院内・外注検査として実施し、結果に応じて治療方針を調整します。 |
| 頭部MRI・脳血管画像 | 脳梗塞・水頭症・脳腫瘍など、パーキンソン病に似た症状を起こす病気の有無を確認します。 | 近隣の画像診断施設・基幹病院に紹介し、結果を当院で一緒に確認します。 |
| DAT‑SPECT・MIBG心筋シンチグラフィーなどの核医学検査 |
ドパミン神経の働きを評価するDAT‑SPECTや、心臓の交感神経を評価するMIBG心筋シンチグラフィーなどにより、 パーキンソン病とその他のパーキンソン症候群の鑑別に役立つことが知られています[16][18]。 |
必要に応じて実施可能な病院へご紹介し、結果を踏まえて診断・治療方針を相談します。 |
| 薬物治療の調整 | レボドパを中心に、ドパミン作動薬・MAO‑B阻害薬などを組み合わせて症状と副作用のバランスをとります[4]。 | 日常生活やお仕事の状況を伺いながら、オーダーメイドに近い形で処方を調整します。 |
| リハビリ・運動療法のご提案 | 運動・バランス訓練・理学療法が運動症状や生活の質の改善に役立つことが分かっています[5][6]。 | 地域のリハビリ施設や訪問リハビリと連携し、患者さんごとに続けやすい運動プランを提案します。 |
| 進行期治療(LCIG・持続皮下注・DBS)の相談・紹介 | 内服薬だけではコントロールが難しくなった場合に、持続投与療法や脳深部刺激療法(DBS)が選択肢になります[12][13][14]。 | 「そろそろ次のステップを考えるべきか?」という時点で、適切な専門施設へ紹介し、治療法の選択を一緒に検討します。 |
受診をお考えの方へ
「こんな症状があればご相談ください(パーキンソン病)」のチェックリストに当てはまる方や、
「このふるえや歩きにくさがパーキンソン病なのか心配」と感じておられる方は、お一人で抱え込まず、どうぞ一度ご相談ください。
吉祥寺駅南口から徒歩1分の当院で、神経内科専門医が現在の状態を丁寧に評価し、今後の見通しや治療の選択肢について分かりやすくご説明いたします。
「まずは話だけ聞きたい」「精密検査が必要かどうか知りたい」「薬を使ったほうが良いか相談したい」といった段階でも、 遠慮なくご相談ください。
当院には、武蔵野市・三鷹市・杉並区だけでなく、 その他東京23区、調布市・小金井市や都外などからも、パーキンソン病やその疑いで多くの方が受診されています。
よくある質問(FAQ)
Q1. パーキンソン病は治りますか?
現在、原因そのものを止める「治す」治療は確立していませんが、症状を和らげて生活の質を保つ治療は大きく進歩しています。お薬の調整やリハビリ、必要に応じて進行期治療を組み合わせます[3][4]。
Q2. どの科を受診すればよいですか?
脳神経内科(神経内科)が専門です。当院でも診断から治療、生活支援まで丁寧に対応します。
Q3. レム睡眠行動障害があると、必ずパーキンソン病になりますか?
必ずではありませんが、長期的にパーキンソン病などに移行する人が多いことがわかっています[9]。定期的なフォローと安全対策が大切です。
Q4. 遺伝の心配があります。検査は受けた方がよいですか?
遺伝性は全体の一部で、多くは家族歴のない散発例です。若年発症・家族歴がある方などは検査を検討します。結果の解釈には専門的なカウンセリングが有用です[3]。
Q5. レボドパはいつから始めるべきですか?
症状で生活に支障が出てきたら時期を選ばず開始できます。初期治療の第一選択とされます[4]。
Q6. 車の運転はできますか?
個人差があります。眠気・注意力への影響や薬の副作用がないかを主治医と確認し、安全を最優先で判断します。
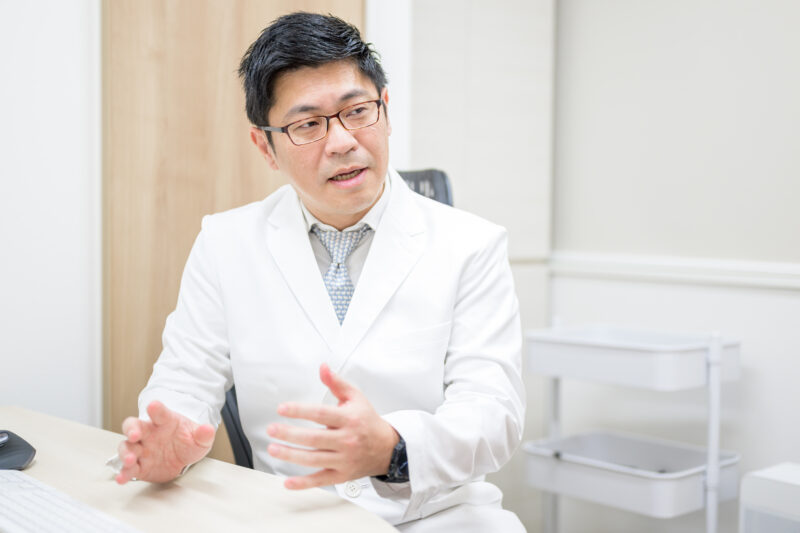
参考文献
参考文献を開く/閉じる
- [1] Postuma RB, et al. MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson’s disease. Mov Disord. 2015. PubMed
- [2] Pereira GM, et al. Global prevalence of Parkinson’s disease: meta‑analysis. npj Parkinson’s Disease. 2024. Publisher
- [3] Bloem BR, Okun MS, Klein C. Parkinson’s disease. The Lancet. 2021;397:2284–2303. PubMed
- [4] AAN guideline: Early PD pharmacologic treatment. Neurology. 2021. PubMed
- [5] Shu HF, et al. Aerobic exercise for Parkinson’s disease: systematic review and meta-analysis. Parkinsonism Relat Disord. 2014. PubMed
- [6] Corcos DM, et al. A two-year randomized controlled trial of progressive resistance exercise for Parkinson’s disease. Mov Disord. 2013. PubMed
- [7] Berg D, et al. MDS research criteria for prodromal PD. Mov Disord. 2015/2019 update. PubMed
- [8] Miyamoto T, et al. The REM sleep behavior disorder screening questionnaire: validation study of the Japanese version (RBDSQ‑J). Sleep Med. 2009;10(10):1151–1154. Europe PMC
- [9] Postuma RB, et al. Prognosis of PSG‑confirmed idiopathic RBD. Brain. 2019;142(3):744–759. PubMed
- [10] AASM guideline for RBD management. J Clin Sleep Med. 2023. PubMed
- [11] Systematic review on clonazepam for RBD (observational). 2022. PubMed
- [12] Olanow CW, et al. LCIG 12‑week RCT. Lancet Neurol. 2014. PubMed
- [13] Careskey J, et al. Foslevodopa/foscarbidopa (subcutaneous levodopa prodrug) in advanced Parkinson’s disease. Neurology. 2024. PubMed
- [14] AAN practice guideline on DBS for PD. 2018. PubMed
- [15] Allen NE, et al. Prevention of Falls in Parkinson’s Disease: A Systematic Review. J Neurol. 2013. PubMed
- [16] Booij J, et al. The clinical use of DAT SPECT imaging in movement disorders. Clin Transl Imaging. 2015. PubMed
- [17] Dorsey ER, Bloem BR. The Parkinson Pandemic—A Call to Action. JAMA Neurol. 2018;75(1):9–10. PubMed
- [18] Pitton Rissardo J, Fornari Caprara AL. Cardiac 123I‑Metaiodobenzylguanidine (MIBG) Scintigraphy in Parkinson’s Disease: A Comprehensive Review. Brain Sci. 2023;13(10):1471. PubMed
