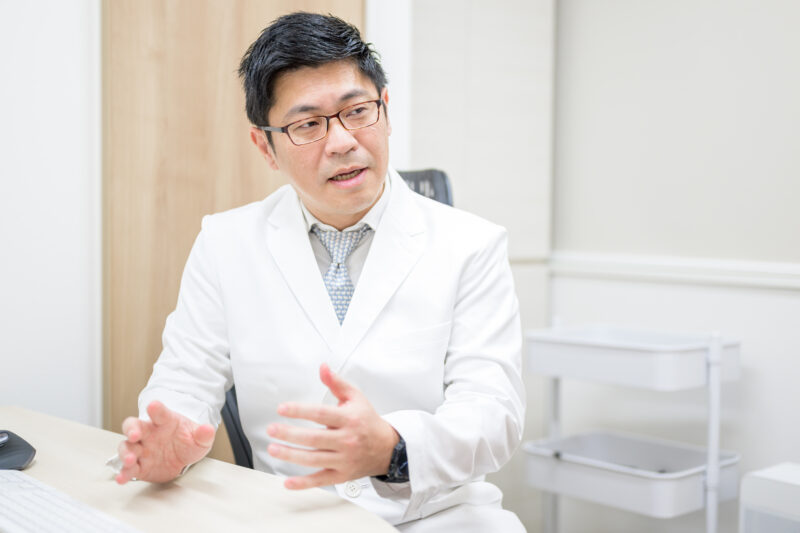認知症の予防|修正可能な因子にもとづく予防とケア(Lancet 2024)
ランセット委員会 2024年報告は、認知症の修正(改善)できる危険因子を14項目に整理し、社会全体では約45%を減らせる可能性があると推定しました。
新しく「中年期の高LDLコレステロール」と「未治療の視力の問題」が追加されています。[1]
この報告は、教育・聴力・血圧・血糖・脂質・喫煙・飲酒・うつ・運動不足・社会的孤立・頭部外傷・大気汚染・視力などを子ども〜若年・中年・高齢というライフコースの流れで整理しています。
特に補聴器の装用、うつの治療、禁煙、空気環境の改善、そして中年期の高LDLの管理は、エビデンスが強いとまとめられています。[1]
詳しく見る
吉祥寺おおさき内科・脳神経内科は「修正可能な因子」に着目し、認知症のリスク低減をめざす実践を行います。
神経内科専門医/総合内科専門医の院長が、脂質・血圧・血糖・活動量・社会的つながりなどを丁寧に評価し、脂質・血圧・血糖の管理、運動・禁煙・減酒などを組み合わせて一人ひとりに合った計画を作ります。
- 「もの忘れが増えた」「言葉が出にくい」「ふらつきが気になる」などの症状が心配な方
- ご家族に認知症の方がいて、ご自身の将来のリスク管理を始めたい方
- 将来のために、今できる予防(生活習慣・医療的サポート)を始めたい方
初診では症状の経過・生活状況を丁寧に伺い、必要に応じて採血・画像・認知機能検査を選択します。
当院は吉祥寺駅(公園口)徒歩1分。武蔵野市・三鷹・杉並から通院しやすい場所です。
目次
本ページの解説
認知症は高齢化とともに世界で増えており、本人・家族・社会の負担が大きい病気です。Lancet 2024は、過去の報告(2017・2020)の更新として、「生活や医療の工夫で減らせる危険因子」に注目しました。新たに中年期の高LDLと視力の問題(未治療)を追加し、ライフコースの各段階(幼少〜若年・中年・高齢)で取り組める内容に整理しています。
ここで出てくるPAF(人口寄与割合)は、「もし社会全体からある危険因子を取りのぞけたら、理論上どのくらい患者数が減る可能性があるか」という推定値です。PAFは因果を確定する数値ではなく、観察研究に由来する限界(交絡・測定誤差など)があります。合計約45%は、因子の重なりを調整した概算で、個人の将来を確実に予測する数字ではありません。あくまで社会や医療の方向性を示す目安として活用します。
- 重要な考え方:認知症のリスクへの対策は早く始めて続けるほど効果的ですが、いつからでも遅くありません(特に中年期の対策が有効)。
- 公平性:教育・住環境・大気汚染・医療アクセスなど、個人だけでは変えにくい要因もあるため、地域や政策レベルの取り組みも重要です。
- 研究の根拠:大規模コホートやメタ解析に加え、一部の介入(例:補聴器・血圧管理など)は介入研究やメカニズム研究でも裏づけが進んでいます。
- 含めなかった候補:睡眠不足、特定の食事法、感染症などは検討されましたが、現時点の証拠のまとまりから公式14因子には含めない結論です(今後の研究で変わる可能性あり)。
修正可能な14因子(ライフコース別)
PAFの合計は約45%です。各因子を減らせたときに、社会全体で減らせる可能性のある割合のイメージとしてご覧ください。[1]
| ライフステージ | 因子 | PAF(%) |
|---|---|---|
| 早期(幼少期〜若年) | 教育年数が少ない | 5 |
| 中年期 | 未治療の聴力低下 | 7 |
| 高LDLコレステロール | 7 | |
| うつ | 3 | |
| 頭部外傷(TBI) | 3 | |
| 身体不活動(運動不足) | 2 | |
| 糖尿病 | 2 | |
| 喫煙 | 2 | |
| 高血圧 | 2 | |
| 肥満 | 1 | |
| 過量飲酒 | 1 | |
| 高齢期 | 社会的孤立 | 5 |
| 大気汚染 | 3 | |
| 未治療の視覚障害 | 2 | |
| 合計(重なり補正後) | 約45 | |
因子別:具体アクション(個人と医療)
認知症のリスクへの対策のポイントは「早く始めて、続ける」こと。ただし今からでも遅くありません。できるところから一緒に進めましょう。[1]
- 聴力低下(PAF 7%):聴力検査+補聴器の装用を検討。補聴器は他のリスクを持つ人ほど効果が大きいことが示されています。
- 高LDL(PAF 7%:中年期):食事・運動・薬物療法(例:スタチン)で管理。認知症そのものの一次予防を直接示す長期試験は限られますが、心血管病の予防効果は確立しており、総合的に管理する価値ありです。
詳しくはこちら(脂質異常症の解説) - うつ(PAF 3%):スクリーニング→心理社会的支援/薬物療法。
- 頭部外傷(PAF 3%):ヘルメットの着用、スポーツでの頭部衝突の回避、受傷後の復帰基準の順守。
- 運動不足(PAF 2%):有酸素+筋力+バランス運動を週合計150分を目安に。
- 糖尿病(PAF 2%):早期診断と血糖管理。
詳しくはこちら(糖尿病の解説) - 喫煙(PAF 2%):禁煙補助薬+行動療法で禁煙サポート。
- 高血圧(PAF 2%):家庭血圧も活用し、目標を決めてコントロール。
詳しくはこちら(高血圧症の解説) - 肥満(PAF 1%):栄養・運動・行動療法を組み合わせ、無理なく継続。
- 過量飲酒(PAF 1%):量と頻度を見直し、減酒支援を活用。
- 教育(PAF 5%):若い時期の教育だけでなく、生涯学習もプラスです。
- 社会的孤立(PAF 5%):家族・友人・地域活動・ボランティア等でつながりを増やす。
- 大気汚染(PAF 3%):住環境・通学/通勤ルートを見直し、地域の改善活動にも参加。
- 視覚障害(PAF 2%):眼科受診・矯正・白内障や緑内障、糖尿病網膜症の治療。多くは治療で改善が期待できます。
当院での評価・スクリーニング
- リスクチェック:血圧・脂質(LDL)・血糖・BMI・喫煙/飲酒・社会参加・頭部外傷歴などを総合評価します。
- 生活習慣病の管理:高LDLコレステロール・高血圧・糖尿病を内科外来で丁寧にフォロー。
- 感覚の最適化:聴力評価→補聴器導入支援、眼科連携(矯正・白内障など)。
- 禁煙・減酒・運動:保健指導と薬物療法を組み合わせ、続けやすい計画を一緒に作ります。
よくある質問(FAQ)
Q1.認知症のリスクへの対策は何歳から始めれば良いですか?今からでも間に合いますか?
A:理想は早く始めて長く続けることですが、いつからでも遅くありません。中年期以降でも、聴力・視力の治療、血圧/血糖/脂質の管理、禁煙、運動量の増加は意味があります。[1]
Q2.優先して取り組むと良いのは?
A:PAFが大きいのは聴力低下(7%)と高LDLコレステロール(7%)です。次いで教育(5%)、社会的孤立(5%)などが続きます。年齢や体質、生活との両立を考えて、優先順位を一緒に決めていきます。[1]
Q3.食事や睡眠は大切ではないのですか?
A:健康的な食事や十分な睡眠はとても大切です。ただ、Lancet 2024の「公式14因子」には、現時点の証拠のまとまりの理由から含めていません(今後変わる可能性はあります)。[1]
Q4.スタチンを飲めば認知症を防げますか?
A:中年期の高LDLコレステロールはリスクですが、認知症そのものの一次予防を直接示す長期試験はまだ少ないです。一方で心筋梗塞や脳卒中の予防にははっきり効果があるので、総合的に見て管理する価値は十分です。[1]
Q5.睡眠時無呼吸を改善すると認知症リスクは下がりますか?
A:現時点では、睡眠時無呼吸(OSA)の治療で認知症の発症が長期的に減ると断定できる決定的な証拠は不足しています。一方で、OSAと認知機能低下の関連を示す研究は増えており、治療(例:CPAP)で短期的に注意力や記憶が改善する報告もあります。Lancet 2024ではOSAは公式14因子に含めていませんが、日中の眠気・いびき・高血圧や肥満がある方は評価を受け、睡眠検査・CPAP・体重管理などを検討する価値があります(全身の健康改善と潜在的な認知保護のため)。[1]