脳ドックの「異常・所見」を、総合内科×脳神経内科の視点で安全に評価・予防へ
脳ドックで未破裂脳動脈瘤/白質病変・無症候性脳梗塞(慢性虚血性変化)/脳微小出血(CMB)/脳萎縮/頭蓋内・頸動脈狭窄・プラークなどを指摘された方へ。
当院では、所見の意味をわかりやすくご説明し、必要十分な追加検査と生活習慣・薬物治療による全身リスク管理、必要時の専門連携まで丁寧に行います。
目次
- 脳ドックの異常所見
- 未破裂脳動脈瘤
- 慢性虚血性変化(白質病変・無症候性脳梗塞)
- 脳微小出血
- 脳萎縮
- 頭蓋内・頸動脈狭窄/プラーク
- 当院の対応内容(診療・検査・連携体制)
- よくあるご質問(FAQ)
- 引用文献
脳ドックの異常所見のポイント
| 所見 | 初診での評価 | 対応・連携・フォロー |
|---|---|---|
| 未破裂脳動脈瘤 | 画像のサイズ・部位・形状と破裂リスク因子(年齢・高血圧・喫煙・家族歴など)を確認します。必要なら追加画像を連携施設に依頼します。 |
|
| 無症候性脳梗塞/白質病変(慢性虚血性変化) | 血圧・脂質・血糖・喫煙・体重などの危険因子と症状の有無を確認します。必要に応じて頸動脈・頭蓋内血管も評価します。 |
|
| 脳微小出血(CMB) | 出血の部位・数・分布と、抗血小板薬・抗凝固薬などの服薬状況を確認します。 |
|
| 脳萎縮 | 萎縮の分布・程度(海馬や側頭葉など)と年齢相応かを確認します。物忘れなどの症状の有無や、睡眠・うつ・薬剤・栄養・甲状腺など二次性要因も評価します。 |
|
| 頭蓋内・頸動脈の狭窄/プラーク | 狭窄の程度やプラークの性状をレポートで確認し、必要に応じてMRAや頸動脈エコーを追加します。 |
|
まとめると:多くの方は緊急手術不要です。まず血圧を中心に全身リスクを整えること、そして6〜12か月を目安に画像や数値を見直すことが基本です。
※上記は無症候を前提にした一般的な流れです。実際の方針は年齢・併存症・所見の性状で個別に調整します。
脳ドックでの各異常所見について
未破裂脳動脈瘤
まとめると:小さく低リスクの動脈瘤は経過観察が基本。血圧管理・禁煙が破裂リスク低減の土台で、高リスクは外科と連携します。
慢性虚血性変化(白質病変・無症候性脳梗塞)
まとめると:脳小血管病のサインなので、まずは血圧、次に脂質・血糖・禁煙・運動。抗血小板薬は所見だけを理由に一律開始しません。
脳微小出血(CMB)
まとめると:最優先は血圧。抗血栓薬は数・分布・併存疾患で出血と梗塞のリスクを秤にかけ、個別判断します。
脳萎縮
- 概要:脳全体や海馬などの体積が小さく見える状態です。年齢による変化もありますが、海馬の萎縮や進み方が速い場合は注意が必要です13,14,15,16。
- 起こりやすい症状:初期は無症状のこともありますが、物忘れや注意力の低下がみられることがあります。
- 将来リスク:海馬の体積が小さい、または萎縮が速いほど、将来の認知症や機能低下と関連します13,14,15。
- 対策(当院):睡眠・うつ・薬剤・栄養(B12)・甲状腺などの二次性要因を見直し、血圧・脂質・血糖管理と運動・禁煙などを整えます。必要に応じて記憶外来と連携します16。
- 関連:認知症との関係が強い所見です。脳卒中とは、共有する血管危険因子(高血圧など)を介して関係します6。
まとめると:年齢相応かどうかを見極め、二次性要因の点検+血圧・脂質・血糖管理を優先。必要に応じて記憶外来へ。
頭蓋内・頸動脈狭窄/プラーク
- 概要:動脈硬化で血管の内腔が狭くなる状態です。症状がある方や高度の狭窄では脳梗塞の危険が高くなります。
- 起こりやすい症状:無症状で見つかることもありますが、TIA(短時間の麻痺や言葉のもつれ)や脳梗塞の既往がある場合は注意が必要です。
- 将来リスク:頭蓋内狭窄は集中的内科治療がステントより優れる成績です9。頸動脈の症候性高度狭窄では内膜剥離術(CEA)が有効です10。ステント(CAS)とCEAは長期成績はほぼ同等ですが、周術期の合併症が異なります11。無症候ではまず厳格な内科治療を行い、条件を満たせば介入を検討します12。
- 対策(当院):禁煙・食事・運動とスタチン等の薬を組み合わせ、血圧や血糖も整えます。必要に応じて血管内治療・外科に迅速にご紹介します。
- 関連:脳卒中との関係が最も強い所見です。認知機能との関連も報告されていますが、まずは脳梗塞の予防を優先します。
まとめると:第一選択は厳格な内科治療。症候性・高度狭窄・不安定プラークでは速やかに専門へ連携し、再発予防を最優先します。
当院の対応内容(診療・検査・連携体制)
- 画像とレポートの再確認:サイズ・部位・形状・狭窄率・プラーク性状/萎縮の分布などを丁寧に確認します。
- 全身リスクの層別化:血圧・脂質・血糖・喫煙・体重・家族歴などを総合的に評価します。
- 必要十分な追加検査:連携施設でのMRAや頸動脈エコーなどを適切に選択します。
- 内科的管理:生活習慣の最適化と、スタチンなどの薬物療法を組み合わせます。
- 迅速な専門連携:治療適応が疑われる場合、脳神経外科・血管内治療・記憶外来へ速やかにご紹介します。
まとめると:画像の読み直し+リスク層別化を起点に、生活×薬物療法と地域の専門連携を一体化して進めます。
よくあるご質問(FAQ)
Q1.未破裂脳動脈瘤はどのくらい破裂しますか?
A:全体の目安は約0.5〜1%/年です。ただし、7mm以上、前交通・後交通・後方循環などの部位、とげ(daughter sac)の有無で変わります。5年リスクはPHASESスコアで推定できます。1,2,3
Q2.白質病変や無症候性脳梗塞があると、認知症や脳卒中の危険は高いですか?
A:白質病変は将来の脳卒中(約2〜3倍)と認知症(約1.5〜2倍)の危険上昇と関連します。無症候性脳梗塞も認知症・脳卒中の危険上昇と関連します。危険因子を総合的に整えることが大切です。4,5,6
Q3.脳微小出血があります。抗血小板薬や抗凝固薬は使えませんか?
A:一律の中止ではありません。脳出血の危険は上がりますが、同時に虚血性脳卒中の危険も上がります。数と分布、ほかの病気やお薬を踏まえて、出血と梗塞のバランスで個別に判断します(心房細動では一般にDOACの方がVKAより出血が少ない傾向があります)。6,7,8
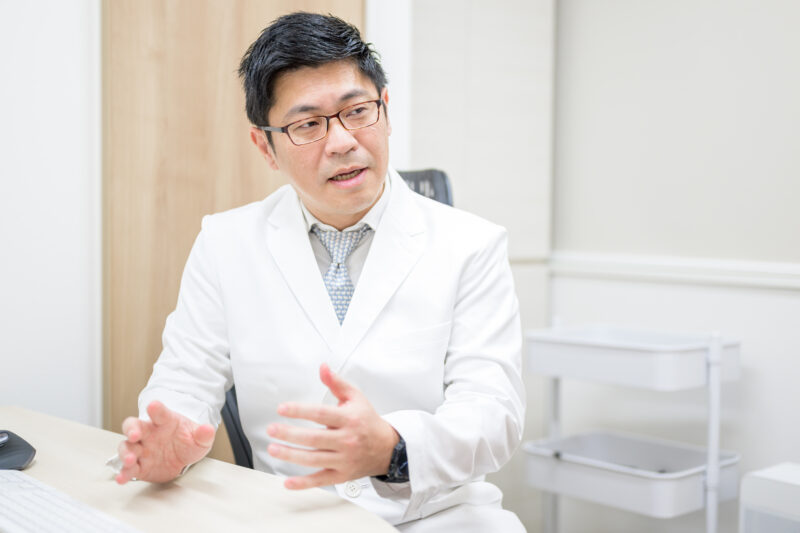
引用文献
引用文献を開く/閉じる
- Morita A, et al. The natural course of unruptured cerebral aneurysms in a Japanese cohort (UCAS Japan). N Engl J Med. 2012;366:2474–2482.
- Greving JP, et al. Development of the PHASES score for prediction of risk of rupture of intracranial aneurysms. Lancet Neurol. 2014;13:59–66.
- Thompson BG, et al. Guidelines for the management of patients with unruptured intracranial aneurysms. Stroke. 2015;46:2368–2400.
- Debette S, Markus HS. The clinical importance of white matter hyperintensities on brain MRI. BMJ. 2010;341:c3666.
- Vermeer SE, et al. Silent brain infarcts and the risk of dementia and cognitive decline. N Engl J Med. 2003;348:1215–1222.
- Debette S, Schilling S, Duperron M-G, Larsson SC, Markus HS. Vascular brain injury and clinical outcomes: a state-of-the-art review. JAMA Neurol. 2019;76:81–94.
- Wilson D, et al. Cerebral microbleeds and intracranial haemorrhage risk in anticoagulated patients. Lancet Neurol. 2018;17:539–547.
- Charidimou A, et al. Cerebral microbleeds and recurrent stroke risk: meta-analysis. Stroke. 2013;44:995–1001.
- Chimowitz MI, et al. Stenting vs aggressive medical therapy for intracranial arterial stenosis (SAMMPRIS). N Engl J Med. 2011;365:993–1003.
- Barnett HJM, et al. Benefit of carotid endarterectomy in symptomatic severe stenosis (NASCET). N Engl J Med. 1991;325:445–453.
- Brott TG, et al. Stenting vs endarterectomy for carotid-artery stenosis (CREST). N Engl J Med. 2010;363:11–23.
- Executive Committee for ACAS. Endarterectomy for asymptomatic carotid stenosis (ACAS). JAMA. 1995;273:1421–1428.
- den Heijer T, et al. A 10-year follow-up of hippocampal volume on MRI in aging and dementia. Brain. 2010;133:1163–1172.
- den Heijer T, et al. Hippocampal and amygdalar volumes to predict dementia in cognitively intact elderly. Arch Gen Psychiatry. 2006;63:57–62.
- Sluimer JD, et al. Whole-Brain Atrophy Rate and Cognitive Decline: Longitudinal MR Study. Radiology. 2008;248:590–598.
- Frisoni GB, Fox NC, Jack CR, Scheltens P, Thompson PM. The clinical use of structural MRI in Alzheimer disease. Nat Rev Neurol. 2010;6(2):67–77.
