言語障害について:失語症・構音障害・発語失行
吉祥寺おおさき内科・脳神経内科は吉祥寺駅徒歩1分です。武蔵野市、三鷹市、杉並区などの方も通いやすいクリニックです。
脳神経内科の医師(日本神経学会 神経内科専門医)/総合内科専門医の院長が、「いつから」「突然かゆっくりか」「どのような場面で困るか(聞く・話す・読む・書く)」を丁寧にお聞きし、必要に応じて神経学的診察、頭部MRI(拡散強調(DWI))/MRA、血液検査などを手配いたします。
詳しく見る
受診の目安:
・急にことばが出ない/ろれつが回らない、さらに片手・片足に力が入らない、顔がゆがむ、視野が欠けるなどを伴うときは、脳卒中の可能性があるため救急受診をお願いします。
・数分〜数十分で自然によくなっても、一過性脳虚血発作(TIA)のことがあり、早めの評価が大切です。
・ゆっくり悪化する場合は、変性疾患・腫瘍・てんかんなどの検査が必要です。
目次
- 緊急性の高い言語障害
- まず押さえる3分類(失語症/構音障害/発語失行)
- 構音障害とは
- 失語症とは
- 失語症の種類
- ろれつが回らない場合の原因(原因の整理を含む)
- 言語障害の検査方法
- 当院での対応
- よくあるご質問(FAQ)
- 参考文献
【直ちに救急対応が必要な「言語障害」】
- 突然、「ことばが出ない」「相手の言うことが分からない」「ろれつが回らない」と気づき、片側の手足の力が入らない、顔がゆがむ、視野が欠けるなどを伴うとき(脳卒中の疑い)。
- 数分〜数十分で一度よくなる場合でも、TIA(一過性脳虚血発作)の可能性があり、速やかな受診が必要です。
- 激しい頭痛・けいれん・高い熱・意識がもうろうといった症状を伴うとき(くも膜下出血・脳炎などの可能性)。
迷ったときは#7119(救急相談センター)に相談し、指示に従って救急受診をご検討ください。
緊急性の高い言語障害(一覧)
| 緊急度 | 病気の例 | どんな様子? | 目安・ポイント |
|---|---|---|---|
| 超緊急 | 脳卒中(大脳半球・脳幹) | 急に始まることばの障害(失語・構音障害)。片麻痺、顔のゆがみ、視界の異常を伴いやすい。 | 救急外来での迅速な評価が必要です。[1] |
| 超緊急 | くも膜下出血 | 突然の強い頭痛に続いて、ことばが出にくい・意識がもうろうとする。 | 吐き気、首が動かしにくいなどを伴うことがあります。救急要請をお願いします。 |
| 緊急 | 脳炎・髄膜炎 | 発熱・頭痛・けいれんと一緒にことばの障害が出る。 | 意識の低下や首のこわばりを伴うことがあります。 |
| 緊急 | TIA(一過性脳虚血発作) | 数分〜1時間ほどで一時的にことばが出にくくなる、ろれつが回らない。 | その後の脳梗塞予防のために、早い受診が大切です。 |
まず押さえる3分類(失語症/構音障害/発語失行)
| 分類 | どんな状態? | よくある原因 | 見分けるポイント |
|---|---|---|---|
| 失語症 | 言いたい言葉が出てこない/相手の言うことが分かりにくいなど、言葉の内容の問題が中心です。 | 脳梗塞・脳出血・外傷・腫瘍・変性疾患など(多くは左半球)。 | 言い間違いや理解のしにくさが目立ちます。[1] |
| 構音障害(Dysarthria) | 舌や口の動かしにくさなど、発音の運動の問題が中心です。意味は伝わっています。 | 脳幹・小脳の障害、パーキンソン病、ALS、重症筋無力症など。 | 聞き取りにくいが、内容は合っていることが多いです。[3] |
| 発語失行(Apraxia of Speech:AOS) | 音の並べ方や動かし方のプログラムが乱れて、ゆっくり・努力して話すのが特徴です。 | 脳梗塞、原発性進行性失語(PPA)など。 | 長い言葉や復唱で間違いが増える傾向があります。[2] |
構音障害とは
構音障害は、舌・口唇・軟口蓋・声帯などの発音に関わる動きがうまく働かず、言葉がはっきり聞こえにくくなる状態です。言葉の意味や理解は比較的保たれます。原因は脳卒中、神経の病気、筋肉の病気、薬の影響などさまざまです。[3]
| タイプ(例) | 主な原因の場所 | 話し方の特徴 |
|---|---|---|
| 痙性タイプ(筋肉がこわばる) | 脳から口の動きに命令を送る道(皮質延髄路)の障害 | 硬い声、ゆっくり、単調になりやすい |
| 弛緩性タイプ(筋力が弱い) | 下位脳神経や末梢神経 | 鼻声、声が弱い、破裂音が不明瞭 |
| 運動低下性(パーキンソン病など) | 基底核の回路 | 小さな声、早口、単調で明瞭度が下がる |
| 運動過多性 | 基底核 | 不随意運動により途切れ途切れになる |
| 小脳性 | 小脳 | リズムが不規則で断綴(だんてつ)言語になる |
| 片麻痺に伴うタイプ | 片側の運動の通り道(皮質延髄路)の障害 | 軽い歪み、少し粗い声 |
脳卒中に伴う構音障害では、評価の方法をそろえることや目標を明確にすることが大切だと報告されています。[4]
失語症とは
失語症は、脳の言語ネットワークの障害により、話す・聞く・読む・書くのどれか(多くは複数)がうまくいかなくなる状態です。一番多い原因は脳卒中で、左の脳の言語に関わる領域の障害で起こりやすいです。診断には診察、MRIなどの画像検査、言語機能の評価を組み合わせます。[1]
見分けのヒント
- 突然起きたら、まず脳卒中を除外します。
- 言い間違いや理解のしにくさが目立てば失語症の可能性があります。
- 書く・理解は保たれていて、滑舌だけ悪いときは構音障害を考えます。
- 音の順序が乱れる、長い言葉でミスが増えるときは発語失行も考えます。
失語症の種類(代表的な古典分類)
表の「流暢性」は話し方の滑らかさ、「復唱」は聞いた言葉をそのまま言い直す力を表します。
| 型 | 流暢性 | 理解 | 復唱 | 主な特徴 | 主な部位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブローカ | 非流暢 | 比較的よい | 低下 | 努力して短い言い方になる。書くときもぎこちない。 | 前頭葉(下前頭回) |
| ウェルニッケ | 流暢 | 低下 | 低下 | 言葉は流暢だが内容が伝わりにくい。言い間違いが多い。 | 側頭葉(上側頭回後部) |
| 伝導 | 流暢 | 比較的よい | 大きく低下 | 復唱がとても苦手。自分で言い直そうとする。 | 弓状束・縁上回 |
| 全失語 | 非流暢 | 低下 | 低下 | 話す・理解の両方が大きく障害される。 | 広い範囲 |
| 超皮質性運動 | 非流暢 | よい | 保たれる | 自分からは話しにくいが復唱は得意。 | 前頭葉内側など |
| 超皮質性感覚 | 流暢 | 低下 | 保たれる | オウム返し(反響言語)が目立つ。 | 頭頂後部〜側頭葉周辺 |
| 失名(失語) | 流暢 | 比較的よい | 比較的保たれる | 物の名前が出にくい(呼称困難)。 | 側頭葉下部〜角回など |
実際の患者さんでは混ざった特徴が見られることも多く、検査結果と合わせて総合的に判断します。[1]
ろれつが回らない場合の原因
「ろれつが回らない」は構音障害(発音の動きの問題)であることが多いですが、失語症や発語失行でも起こります。
| 大きな分類 | 代表的な病気 | 一緒に出やすい症状 | 受診の目安 |
|---|---|---|---|
| 脳・脊髄(中枢神経) | 脳梗塞・脳出血(大脳/脳幹)、小脳の障害、脱髄(多発性硬化症) | 突然の発症、片麻痺、顔のゆがみ、ふらつき など | ただちに救急。[1] |
| てんかん関連 | 一時的に話せない、発作後に言葉が出にくい など | けいれん、同じ動作を繰り返す、発作後のぼんやり | 初めて/繰り返す場合は早めに受診 |
| 神経変性・神経筋 | パーキンソン病、ALS、重症筋無力症、末梢神経障害 | 少しずつ進む小声・単調さ、飲み込みにくさ | 脳神経内科で計画的に評価 |
| 全身・代謝 | 低血糖、肝・腎の機能低下、甲状腺の異常、脱水・電解質異常 | 強いだるさ、意識がもうろう、ふらつき | 体調不良が強いときは救急 |
| 薬・アルコール・中毒 | 睡眠薬・抗てんかん薬・アルコール など | 眠気、ふらつき、記憶の不調 | 服薬・飲酒の確認。症状が強ければ受診 |
| 口やのどの病気 | 腫瘍、炎症、構造の異常 | かすれ声、鼻声、飲み込み時の痛み | 耳鼻咽喉科と連携 |
| 脳の腫瘍など(ゆっくり進行) | 脳腫瘍、慢性硬膜下血腫 など | 少しずつ進む言葉や記憶の変化、頭痛 | 脳神経内科/脳神経外科へ |
言語障害の検査方法
| 検査 | 何が分かる? | どんなときに? |
|---|---|---|
| 神経学的診察 | 失語症・構音障害・発語失行のどれに当てはまるか、内容の問題か発音の動きの問題かを見極めます。 | 診察時にに行います。 |
| MRI(DWI)/MRA | 脳梗塞や出血、腫瘍などの有無や場所を調べます。 | 突然起きたとき、進行しているときに優先します。 |
| 標準化された言語検査 (例:標準失語症検査:SLTA) |
「話す・聞く・読む・書く」を数値化して得意・苦手を把握します。 | 初期評価と、経過をみるときに行います。 |
| 血液検査 | 低血糖、感染、ホルモンの異常、薬の影響など全身の原因を探します。 | 体調不良や薬の影響が疑われるときに行います。 |
| 心電図・ホルター心電図 | 脳梗塞の原因になりうる不整脈(心房細動など)を調べます。 | 脳梗塞やTIAが疑われるときに行います。 |
当院での主な対応
- 急に始まった症状では、脳卒中を念頭において救急搬送が必要かを判断します。
- 神経学的診察と画像検査(MRI/MRA)、血液検査を組み合わせて原因を探します。
- 必要に応じて耳鼻咽喉科・脳神経外科などと速やかに連携します。
【言語障害】よくあるご質問(FAQ)
A. 受診判断・日常のポイント
「突然ことばが出ない/ろれつが回らない」は救急ですか?
はい、救急の可能性があります。片側の手足の力が入らない、顔のゆがみ、視界が欠けるなどを伴うときは、すぐに救急要請をご検討ください。[1]
一度よくなっても受診は必要ですか?
必要です。数分〜数十分でよくなる言語の症状は、一過性脳虚血発作(TIA)のことがあり、その後の脳梗塞の予防のために早めの評価が大切です。
受診までに家族ができる準備はありますか?
症状が始まった時刻、最初の様子、飲んでいる薬(お薬手帳)をメモしてください。動画で話し方の変化を記録できると、診察の助けになります。
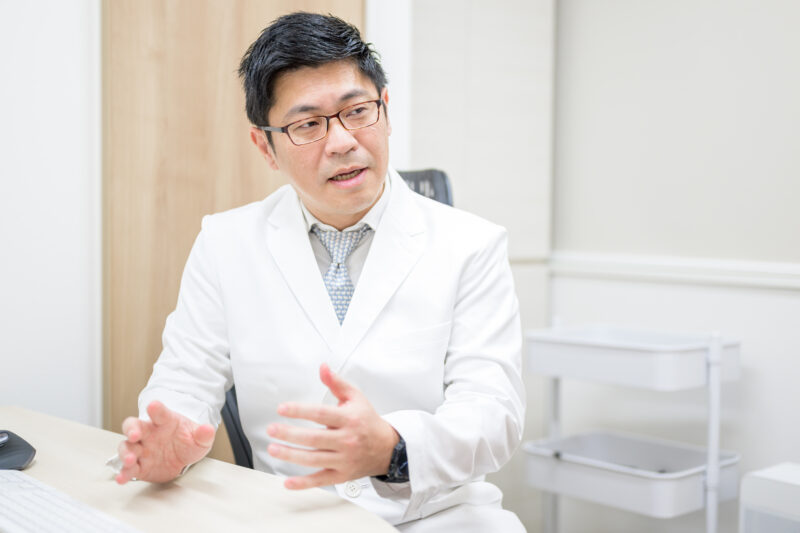
参考文献(エビデンス)
参考文献を開く/閉じる
- Sheppard SM, et al. Diagnosing and managing post‑stroke aphasia. Pract Neurol. 2020.(失語症の臨床整理) PMC
- Ogar J, et al. Apraxia of speech: an overview. Neurocase. 2005;11:427–432. PubMed
- Jayaraman DK, et al. Dysarthria. StatPearls [Internet]. 2023. NCBI Bookshelf
- Lin LX, et al. Stroke‑associated dysarthria. Front Neurol. 2025;16:1629640. Frontiers
