意識障害・痙攣について:失神との違い、原因と受診の目安
吉祥寺おおさき内科・脳神経内科は吉祥寺駅徒歩1分。武蔵野市、三鷹市、杉並区などの方も通いやすいクリニックです。
神経内科専門医/総合内科専門医の院長が、「意識が低下したのはいつから・どれくらい続いたか」「けいれんはあったか」「前駆症状(動悸・冷や汗・胸痛など)はあったか」を丁寧にお伺いし、まずバイタルサイン・血糖測定、必要に応じて心電図・頭部MRI(拡散強調:DWI)/CT、採血、脳波(EEG)の実施・手配を行います。意識レベル評価にはグラスゴー・コーマ・スケール(GCS)を用います。[1]
目次
【直ちに救急対応が必要です】
- けいれんが止まらない/繰り返す(けいれん重積状態(SE)の疑い)
- 片側の手足が動かない・言葉が出ない・顔がゆがむなどの突然の神経症状(脳卒中の疑い)
- 高熱・激しい頭痛・うなじの強いこわばり(髄膜炎/脳炎の疑い)
- 胸痛・動悸・息切れを伴う意識消失(心原性失神の可能性)
- 糖尿病治療中で意識がもうろう(低血糖の可能性)
緊急性の高い症状(一覧)
| 緊急度 | 代表病態 | 症状の簡単な解説 | 主なサイン・初期対応 |
|---|---|---|---|
| 超緊急 | けいれん重積状態(SE) | けいれんが5分以上続く、または意識が回復しないまま繰り返す。 | 気道確保・酸素投与・速やかなベンゾジアゼピン、次段階の静注抗てんかん薬を考慮。[2][3] |
| 超緊急 | 脳卒中(出血・梗塞) | 突然の麻痺・言語障害・視野障害、激しい頭痛や嘔吐を伴うことも。 | MRI(DWI)/CTを含む救急評価。適応により血栓溶解・血管内治療。[4] |
| 緊急 | 心原性失神 | 危険な不整脈や心筋梗塞などで脳血流が一時的に低下。 | 12誘導心電図、SpO2、必要に応じ心エコー・ホルター。[6] |
| 緊急 | 髄膜炎/脳炎 | 高熱、頭痛、項部硬直、意識障害、けいれんなど。 | 抗菌薬/抗ウイルス薬の早期投与を検討。[5] |
| 準緊急 | 初めての失神・初めてのけいれん | 背景に心臓・代謝・脳の病気が隠れていないか評価が必要。 | 問診・診察・血糖・ホルター心電図・画像/脳波の選択的検査。[7][6] |
緊急度の目安:超緊急=直ちに救急対応/緊急=当日中の専門評価(救急含む)/準緊急=1〜3日以内の専門受診。
意識障害とは
「意識障害」は、覚醒(目が覚めている力)や意識内容(周囲を理解し適切に反応する力)が低下した状態を指します。軽いもうろうから深い昏睡まで幅があり、意識状態の評価にはグラスゴー・コーマ・スケール(GCS)が広く使われています。[1]
- よくあるきっかけ:睡眠不足・脱水・発熱・薬/アルコール・低血糖・感染症・脳卒中・頭部外傷など。
- まず確認すること:呼吸(酸素)、循環(脈と血圧)、血糖、体温、けいれんの有無、頭部外傷の既往、薬やサプリの服用歴。
意識障害の原因
| カテゴリー | 具体例 | ポイント |
|---|---|---|
| 脳の病気 | 脳梗塞・脳出血、くも膜下出血、頭部外傷、脳腫瘍、てんかん発作後など | 突然の麻痺・言語障害・強い頭痛は要注意。画像検査を検討。[4] |
| 全身の病気 | 低血糖・低酸素・ショック・敗血症・肝不全/腎不全・電解質異常(ナトリウムなど) | まず血糖・SpO2・体温・血圧の確認。[5] |
| 心血管 | 危険な不整脈、急性冠症候群、大動脈解離、肺塞栓など | 心電図・胸痛/動悸の聴取。[6] |
| 薬物・中毒 | アルコール、睡眠薬・抗不安薬、オピオイド、中毒(一酸化炭素など) | 服薬歴・環境暴露の確認。解毒薬の適応を検討。 |
| 感染症 | 髄膜炎・脳炎、肺炎、尿路感染症など | 高熱・項部硬直・意識低下は救急対応。[5] |
失神とは
「失神」は、一過性の全脳低灌流(脳全体の血流低下)によって起こる、急に始まり短時間で自然に完全回復する意識消失のことです。前ぶれとして冷や汗・吐き気・目の前が暗くなるなどが出ることがあります。[6]
- 典型的な経過:数十秒で回復し、回復後の混乱は短い(数分以内)ことが多い。
- 注意が必要:労作中の失神、心臓病の既往、心電図異常、家族に若年突然死がいる場合は心原性の可能性があります。[6]
失神の原因
失神は大きく反射性(神経調節性・血管迷走神経性)、起立性低血圧、心原性に分けられます(外来全体では反射性が最多)。[6]
| 分類 | よくある誘因・特徴 | 検査の例 |
|---|---|---|
| 反射性(血管迷走神経性・状況失神) | 長時間の立位、痛み、恐怖、採血・排便・排尿など/冷や汗・吐き気の前駆あり | 問診が最重要。必要に応じ循環器内科での傾斜試験。 |
| 起立性低血圧 | 立ち上がって数分以内にふらつき・黒くなる感覚。脱水・薬剤・自律神経障害。 | 起立試験(3分基準)、血圧・脈拍測定。 |
| 心原性 | 労作中・仰臥位での失神、動悸・胸痛を伴う、回復が遅いことも。 | 12誘導心電図、ホルター心電図、心エコー、必要に応じ電気生理学的検査。 |
痙攣の原因
「痙攣(けいれん)」は筋肉が不随意に周期的に収縮する状態で、脳の異常な電気活動(発作)により起こることが多いです。原因は誘発性(provoked)と非誘発性(unprovoked=てんかんの一部)に分けられます。[8][9]
| 区分 | 主な原因 | ポイント |
|---|---|---|
| 誘発性(provoked)/急性症候性発作 | 高熱(小児の熱性けいれん)、低ナトリウム血症・低カルシウム、低血糖、禁酒/離脱、薬剤(例:トラマドールなど)、脳炎・髄膜炎、頭部外傷 など | 原因治療が優先。多くは原因が除かれると再発リスクが低下。 |
| 非誘発性(unprovoked) | てんかん(脳の発作性素因)、脳卒中後・脳腫瘍・先天性構造異常など | 脳波・MRIで評価。てんかんは「2回以上の非誘発性発作」または「1回+再発リスクが高い状況」で診断されます。[8] |
なお、5分以上続くけいれん、または意識が戻らないまま繰り返す場合はけいれん重積状態(SE)で、救急対応が必要です。[2][3]
失神・てんかん発作の見分け方(目撃情報が重要)
意識障害の検査方法(必要に応じて選択)
当院での主な対応
- 問診・神経学的診察・GCSによる重症度と原因の初期評価
- 血糖測定・採血の実施、必要に応じて頭部MRIの手配
- 初めてのけいれんに対する脳波(EEG)や再発リスクの評価(連携施設と協力)
- 心原性失神が疑われる場合のホルター心電図
- 救急対応が必要と判断した場合は同日での救急紹介を行います
【意識障害・痙攣】よくあるご質問(FAQ)
A. 受診判断・緊急性
救急車を呼ぶタイミングは?
5分以上続くけいれん、繰り返すけいれんで意識が戻らない、片麻痺・ろれつ不良、高熱+強い頭痛・項部硬直、胸痛・強い動悸を伴うときは直ちに119番をお願いします。[3][5][6]
舌を噛んだらてんかんですか?
舌の側面の咬傷はてんかんの強い手がかりですが、絶対ではありません。全体の経過と検査で判断します。[10]
けいれんの後に強い眠気やぼんやりがあります
多くの場合は発作後の回復期で、数十分で改善します。ただし長く続く・再発する場合は受診してください。[7]
初めてのけいれんで必ず薬は必要ですか?
原因や再発リスクにより異なります。脳波やMRIでハイリスクが示唆される場合は、内服開始を検討します。[7]
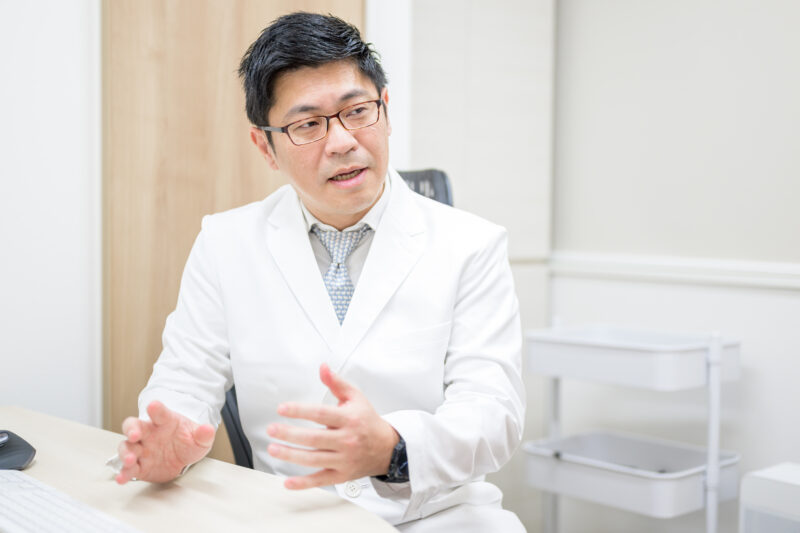
参考文献(エビデンス)
参考文献を開く/閉じる
- Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: A practical scale. Lancet. 1974;2:81–84. PubMed
- Trinka E, et al. A definition and classification of status epilepticus – Report of the ILAE Task Force. Epilepsia. 2015;56:1515–1523. PubMed
- Kapur J, et al. Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus. N Engl J Med. 2019;381:2103–2113. PubMed
- Chalela JA, et al. MRI vs CT for detection of acute stroke. Lancet. 2007;369:293–298. PubMed
- van de Beek D, et al. Community-Acquired Bacterial Meningitis in Adults. N Engl J Med. 2016;375:236–247. PubMed
- Brignole M, et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J. 2018;39:1883–1948. Journal
- Krumholz A, et al. Evidence-based guideline: Management of an unprovoked first seizure in adults. Neurology. 2015;84:1705–1713. PubMed
- Fisher RS, et al. ILAE official report: A practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014;55:475–482. PubMed
- Fisher RS, et al. Operational classification of seizure types by the ILAE. Epilepsia. 2017;58:522–530. PubMed
- Brigo F, et al. The diagnostic value of tongue biting in differentiating epileptic seizures from syncope: a meta-analysis. Epilepsia. 2012;53(11):e1–e5. PubMed
- Sheldon R, et al. Historical criteria that distinguish syncope from seizures. J Am Coll Cardiol. 2002;40:142–148. PubMed
