もの忘れ・認知症について(早期発見と薬物療法)
もの忘れ・認知症外来:当院では神経内科専門医が、神経学的診察・認知機能検査・MRIや核医学検査を組み合わせ、アルツハイマー病・レビー小体型・血管性・前頭側頭葉変性症・正常圧水頭症までを専門的に鑑別いたします。
また、Lancet Standing Commission 2024に準拠し、高血圧・脂質異常症・糖尿病・睡眠時無呼吸・難聴・喫煙などの修正可能な危険因子を体系的に評価し、厳格な血圧管理や脂質低下療法、CPAP、補聴器の活用、禁煙支援などの治療をご提案します。[10]
詳細は院内解説「認知症の修正可能な危険因子(Lancet 2024準拠)」をご覧ください。
目次
もの忘れと認知症の違い
もの忘れは加齢でどなたにも起こり得ます(例:鍵の置き場所を思い出せない)。
一方、軽度認知障害(MCI)は「検査で認知機能の低下が確認できる」段階ですが、日常生活(ADL)は自立しています。さらに進んで、仕事・家事・金銭管理などに支障が出ると認知症と診断されます。
また、高血圧・脂質異常・糖尿病・睡眠時無呼吸・難聴・喫煙・運動不足は対策できるリスクです。早期から整えることが将来の認知症リスク低減につながります。[10]
認知症リスクの低減(修正可能因子)
当院はLancet Standing Commission 2024に基づき、次の項目を系統的に評価・介入いたします。[10]
- 高血圧:生活改善+お薬で厳格に血圧を管理します。[12]
- 脂質異常症:スタチン等で動脈硬化の進行を抑える治療を行います。
- 糖尿病:血糖コントロールと合併症予防を行います。
- 難聴:補聴器の適切な使用を耳鼻科と連携して進めます(大規模試験の成果あり)。[7]
- 睡眠時無呼吸:CPAP等で睡眠の質と血圧を改善します。
- 喫煙・過量飲酒・運動不足:禁煙支援、節酒、有酸素運動+筋力・バランス訓練を勧めます。
- 社会的孤立・抑うつ:活動や交流の機会づくり、必要に応じて心のケアをご提案します。
詳しくは院内解説ページ「認知症の修正可能な危険因子(Lancet 2024準拠)」をご覧ください。
軽度認知障害(MCI)
MCIのポイント
- ご本人・ご家族が「前より物忘れが増えた」と感じ、検査でも同年代より低い成績がみられます。
- 日常生活(ADL)は自立しています(買い物や家計管理などで少し非効率になることはあります)。
- 認知症の基準は満たしません(うつ病や薬の影響、内科疾患など他の原因を確認します)。[11]
※アルツハイマー病が背景のMCIでは、アミロイドやタウの検査が陽性になることがあります。[9]
MCIの評価と対策
- 評価:家族からの聞き取りと認知テスト、必要に応じて詳細検査やMRIで脳の萎縮・血管の変化を確認します。
抗アミロイドβ抗体を検討する場合はアミロイドPETや髄液検査で判断します。[9] - 経過:進む方もいれば一時的に改善する方もいらっしゃるため、定期的なフォローが大切です。[11]
- 対策:運動・認知刺激・睡眠時無呼吸や難聴の是正・禁煙に加え、生活習慣病への薬物治療を組み合わせます。
当院はLancet 2024に準拠し、高血圧・脂質異常症などを認知症の修正可能因子として治療いたします。詳しくは「認知症の修正可能な危険因子」をご参照ください。[10]
認知症の主な種類
1. アルツハイマー病(AD)
疾患の概要:脳にアミロイドβやリン酸化タウがたまり、神経細胞の働きが少しずつ弱っていく病気(神経変性疾患)です。現在はA/T/N(A=アミロイド、T=タウ、N=神経の萎縮・機能低下)という生物学的な考え方で病態を評価します。[9]
- 主な症状:最近の出来事を忘れやすくなることから始まり、進行すると言葉・視空間認知・段取りの力も下がります。
- 画像/検査:MRIで海馬の萎縮、脳血流SPECTで頭頂部〜後部帯状回の血流低下などが参考になります。アミロイドPETや髄液検査は、抗アミロイドβ抗体の適用判定目的に限り保険適用です。[9]
- 治療:認知機能と生活機能を保つことを目的とした標準薬(ドネペジル等)に加え、早期の段階では抗アミロイドβ抗体の選択肢があります。[8][4][5]
2. 血管性認知症(VaD)
疾患の概要:脳の血管の病気(脳梗塞・小さな出血・白質の傷み など)が原因で起こる認知症です。注意力や計画を立てる力の低下、歩きにくさ、階段状に悪くなる経過がみられることがあります。
- 診断:認知機能の低下に加え、画像で原因となる血管性の変化が確認できることが大切です。
- 対策:血圧を厳格に管理すると認知機能低下の予防につながる可能性があります。糖尿病や脂質異常症の治療、禁煙、心房細動の治療も重要です。[12]
- 治療の考え方:再発予防(抗血小板薬・抗凝固薬)と生活習慣の改善が中心です。認知症薬は第一選択ではありません(混合型では検討します)。
3. レビー小体型認知症(DLB)
疾患の概要:αシヌクレインというたんぱく質が脳にたまり、注意や覚醒の波が大きく変動する、実際にはないものがはっきり見える(幻視)、手足のふるえやこわばり(パーキンソン症状)、夢の内容に合わせて体が動く睡眠障害(RBD)などが出やすい病気です。起立性低血圧や便秘などの自律神経症状がみられることもあります。[1]
- 検査の目安:DaT‑SPECT(ドパミントランスポーター)低下、MIBG心筋シンチ低下、レム睡眠行動異常症があると診断を後押しします。[1]
- 画像の特徴:MRIでは内側側頭葉の萎縮が比較的軽いことがあり、脳血流SPECTでは後頭葉優位の血流低下が参考所見です。[1]
- 治療:コリンエステラーゼ阻害薬(例:ドネペジル)が中心。抗精神病薬は副作用が出やすく最小限に。パーキンソン症状が強い場合はレボドパ等を少量から慎重に。[8]
4. 前頭側頭葉変性症(FTLD)
疾患の概要:脳の前頭葉・側頭葉が主に影響を受ける病気で、性格や行動の変化(脱抑制・無関心・常同行動など)やことばの障害が目立ちます。比較的若い世代(50〜60代)で発症することもあります。
- 臨床型:行動変異型FTD、原発性進行性失語(非流暢/文法障害型・意味変化型・ロゴペニック型)があります。[14]
- 支援の考え方:お薬の効果は限定的なことが多いため、環境調整や行動・言語のリハビリ、ご家族のサポートを重視します。[8]
5. 特発性正常圧水頭症(iNPH)
疾患の概要:脳脊髄液の流れがうまくいかず脳室が広がることで、歩幅が小さくなる/すり足になる、もの忘れ、尿がもれるの三つの症状が出やすい病気です。治療可能な認知症の代表であり、正確に診断して適切な治療へつなげることがとても重要です。[15]
- 画像所見:DESH(脳室の拡大+頭頂部のすき間が狭く見える形)などを確認します。[15]
- 診断手順:タップテスト(腰から少量の髄液を抜いて歩きやすさ等が改善するか確認)や持続排液で反応をみます。[15]
- 治療:反応が確認できれば、シャント手術で歩行・認知・排尿の改善が期待できます。[15]
認知症の診断の進め方と評価
- 問診(ご本人・ご家族):いつから・どのように変化したか、睡眠やお薬、気分の変化などを丁寧に伺います。
- 認知機能テスト:HDS‑R・MMSE・MoCA‑Jなどで記憶・注意・言語・視空間などを評価します。
- 血液検査:貧血・甲状腺・ビタミンB1/B12・肝腎機能など、他の原因がないか確認します。
- 画像検査:MRIを基本に、必要に応じて脳血流SPECT・DaT‑SPECT/MIBGなどを追加します。[1]
- バイオマーカー:アミロイドPETや髄液検査(抗アミロイドβ抗体の適用判定目的に限り保険適用)。[9]
- 睡眠:睡眠時無呼吸の有無を評価するため、必要に応じて在宅での簡易睡眠検査を行います。
治療(非薬物+薬物+病態修飾薬)
1)薬を使わない支援
- 運動:中等度の有酸素運動に、筋力・バランス訓練を組み合わせます。
- 認知刺激(CST):会話や学習活動により、気分や生活の質の改善も期待できます。[8]
- 聴こえ・見え方の最適化:補聴器の活用は認知の低下を緩やかにする可能性があります。[7]
- 睡眠時無呼吸の管理:CPAPなどで睡眠の質と血圧を整えます。[10]
2)認知症リスク低減のための治療(修正可能因子への薬物介入)
- 高血圧:個別目標を定め、必要に応じて併用療法で厳格に降圧します。[12]
- 脂質異常症:スタチン等で心血管リスクを低減します。
- 糖尿病:生活指導+薬物療法で血糖を管理します。
当院の方針は「認知症の修正可能な危険因子(Lancet 2024準拠)」をご参照ください。[10]
3)認知機能・生活機能の維持を目的とした標準薬物療法
- アルツハイマー病:ドネペジル・リバスチグミン・ガランタミン、メマンチン(状態に応じて選択)。[8]
- レビー小体型:ドネペジルが基本(日本でDLBの効能あり)。抗精神病薬は最小限に。[8]
- 血管性:認知症薬は第一選択ではなく、まずは血管リスクの是正を重視(混合型は検討)。[8]
- 前頭側頭葉変性症:薬効は限定的。環境調整と家族支援を重視。[8]
4)病気の進みを遅らせる治療(抗アミロイドβ抗体)
対象:軽度認知障害(MCI)または軽度のアルツハイマー病で、アミロイド陽性が確認できた方。
国内承認:レカネマブ(レケンビ®)/ドナネマブ(ケサンラ®)。[4][6]
※アミロイドPET/髄液検査は適用判定目的で保険適用。最適使用推進ガイドラインに準拠します。
安全に使うための準備
- アミロイド陽性の確認(PET/髄液検査)。
- ApoE ε4の説明と検査:ARIA(アミロイド関連画像異常)のリスクに関与。[4][5]
- MRIモニタリング:開始前に基準画像、レカネマブは5・7・14回目前、ドナネマブは2・3・4回目前に確認。[4][5]
- 併用薬の確認:抗凝固薬・抗血小板薬の出血リスクに配慮。[4][5]
治療の進め方(概要)
効果と注意点
- 効果:大きく改善する薬ではなく、進行の速さを抑えることを目指します(例:レカネマブは18か月でCDR‑SBの進行を約27%抑制)。[2][3]
- 副作用(ARIA):脳のむくみ・微小出血など。頭痛・めまい・失語・脱力等に注意し、MRIで確認。※ApoE ε4保有でリスク↑[4][5]
| 項目 | レカネマブ | ドナネマブ |
|---|---|---|
| 対象 | MCI/軽度AD、アミロイド陽性 | |
| 投与間隔 | 2週ごと点滴(まず18か月)[4] | 4週ごと点滴(プラーク除去確認で完了)[5] |
| 主な目的 | 脳のアミロイドを減らし、進行を緩やかにする。[2][3] | |
| 主な注意 | ARIA(脳のむくみ・微小出血)に注意。定期MRIで安全確認。/ ApoE ε4保有でリスク↑[4][5] | |
よくある質問(FAQ)
Q1.年相応の物忘れと認知症はどう違いますか?
A:人名や物の場所が思い出しにくいだけで生活に支障がない場合は、年相応のこともあります。出来事自体を忘れる・生活に支障が出る場合は、MCIや認知症の可能性があります(診断は問診・検査・画像の総合評価で行います)。[11][9]
Q2.軽度認知障害(MCI)はどのくらい進行しますか?
A:個人差が大きく、進む方もいれば改善する方もいらっしゃいます。そのため定期的なフォローが大切です。[11]
Q3.抗アミロイドβ抗体は誰でも使えますか?
A:対象はMCI/軽度アルツハイマー病でアミロイド陽性の方に限られます。MRIでの見守りやARIAへの注意が必要です。
Q4.BPSD(徘徊・攻撃的行動・抑うつ など)の対応は?
A:認知症の中核症状(記憶・判断など)は当院の守備範囲ですが、BPSD(徘徊・攻撃的行動・抑うつ など)の専門的治療は当院では行っておりません。該当する場合は精神科・心療内科・老年精神科の専門外来をご検討ください。
Q6.睡眠時無呼吸を治すと認知機能も良くなりますか?
A:まずは眠気や血圧の改善が期待でき、長期的にも脳の健康に良い影響が見込めます。必要に応じて検査・治療をご一緒に検討いたします。[10]
Q7.レケンビ®(レカネマブ)の費用はどの程度かかりますか?
A:自己負担割合(1〜3割)や高額療養費制度、年齢・所得、公費の有無で異なります。薬剤費に加え点滴管理料・定期MRI・適用判定の検査が含まれます。※レケンビ®は2週ごとの点滴と定期画像モニタリングが必要です。
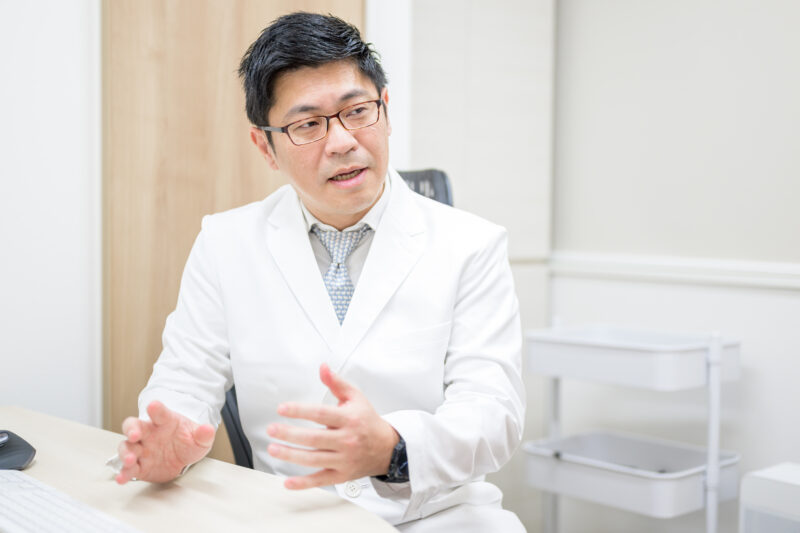
参考文献
参考文献を開く/閉じる
- [1] McKeith IG, et al. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium. Neurology. 2017. PMC
- [2] van Dyck CH, et al. Lecanemab in Early Alzheimer’s Disease (CLARITY‑AD). N Engl J Med. 2023;388:9‑21. NEJM
- [3] Mintun MA, et al. Donanemab in Early Symptomatic Alzheimer Disease (TRAILBLAZER‑ALZ 2). JAMA. 2023;330(6):512‑527. PubMed
- [4] LEQEMBI® (lecanemab) Prescribing Information. 2024. PDF
- [5] KISUNLA™ (donanemab‑azbt) Prescribing Information. 2024. PDF
- [6] 厚生労働省/中医協資料「ケサンラ(ドナネマブ)薬価収載時の対応」2024/9/24. PDF
- [7] Lin FR, et al. Hearing intervention and cognitive decline in older adults: ACHIEVE randomized trial. Lancet. 2023;402:568‑579. PubMed
- [8] NICE Guideline NG97: Dementia: assessment, management and support. 2018. NICE
- [9] Jack CR Jr, et al. 2024 NIA‑AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement. 2024. PubMed
- [10] Livingston G, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet Standing Commission. Lancet. 2024;404:572‑628. Lancet
- [11] Petersen RC, et al. Practice guideline update summary: Mild cognitive impairment. Neurology. 2018;90:126‑135. PMC
- [12] Williamson JD, et al. Intensive vs Standard Blood Pressure Control and Probable Dementia/MCI: SPRINT‑MIND. JAMA. 2019;321(6):553‑561. JAMA
- [13] Neumann M, et al. A new classification scheme for FTLD‑TDP and related pathology. Acta Neuropathol. 2021. PMC
- [14] Gorno‑Tempini ML, et al. Classification of primary progressive aphasia and its variants. Neurology. 2011;76:1006‑1014. PMC
- [15] Nakajima M, et al. Guidelines for Management of Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus (3rd ed.). Neurol Med Chir (Tokyo). 2021. PMC
